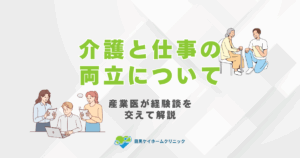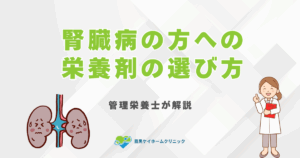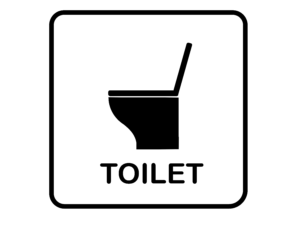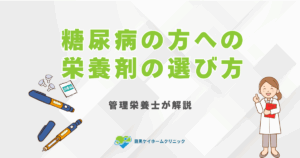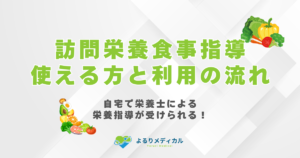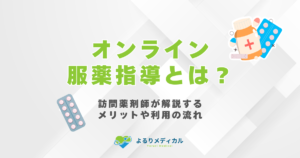在宅で介護をしていると、予期せぬ出来事が起こることがあります。中でも、高齢者の転倒は介護者にとって大きな不安の種です。「どうしたらいいんだろう?」「救急車を呼ぶべき?」と、頭が真っ白になってしまう方も少なくありません。
しかし、慌てずに適切な手順で対応することが、ご本人の安全を守る上で最も重要です。 この記事では、ご自宅で高齢者が転倒してしまった際に、介護の資格がない方でも落ち着いて、そして順を追って対応できるよう、具体的な方法を解説します。また、転倒後の対策や再発予防についても詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
転倒直後:落ち着いて状況を確認
もし、ご自宅で介護されている方が転倒してしまったのを発見したら、まずは深呼吸をして落ち着きましょう。 転倒したご本人も、予想外の事態に動揺しているはずです。 あなたの冷静な対応が、ご本人の安心につながります。
1. 声をかけて意識を確認する まず、「大丈夫ですか?」「聞こえますか?」と優しく声をかけ、意識があるかどうかを確認します。
2. 気持ちを落ち着かせる 「ここにいますよ」「ゆっくりで大丈夫ですよ」といったような、安心できる言葉をかけて、ご本人の不安な気持ちを和らげてください。慌てて体を起こそうとするのは、かえって怪我を悪化させる可能性があるため、絶対に避けましょう。
3. 身体の状態を確認する 転倒したままの姿勢で、どこが痛むか、気持ちが悪いか(吐き気など) をゆっくりと尋ねます。 矢継ぎ早に質問するのではなく、一つずつ丁寧に確認することが大切です。
- 頭部の保護: 可能であれば、近くにあるクッションや枕、座布団などを頭の下にそっと置いて、頭部を安定させましょう。 タオルなどを丸めて代用しても構いません。
- 痛みの確認: 手を握ったり、足を伸ばしたりできるか、股関節などにも痛みがないかなどを確認します。 もし、激しく痛がる部位があれば、無理に動かさないようにしてください。
- 出血の確認: 特に頭部や、ぶつけたと思われる場所に傷がないか、出血がないかを確認します。
4. 転倒時の状況を聞き出す 落ち着いてから、何をしようとして転んでしまったのか、どのような体勢で転んだのか をできるだけ詳しく聞き出します。 これらの情報は、怪我の状態を予測する上で重要な手がかりとなります。
5. 脈を確認する(可能であれば) もし可能であれば、ご本人の脈を確認してみましょう。 手首の親指側にある血管に、人差し指と中指の先を当てて、脈を感じます。 ドクドクと早く脈打っている場合は、まだ焦っている状態なので、落ち着くまで待ちましょう。 その間、優しく声をかけたり、体をさすったりするのも有効です。
救急車を呼ぶべき?判断の目安
身体の状態や転倒時の状況を確認したら、救急車を呼ぶべきかどうかを判断します。以下は、救急車を呼ぶ目安となる症状です。
- 意識がない、または反応が鈍い
- 頭を強く打った(意識消失があった場合は特に注意が必要です)
- 頭部からの出血が止まらない
- 激しい痛みがあり、体を動かせない(骨折の疑いがある場合)
- 呼吸が苦しい、または普段と様子が違う
- 吐き気や嘔吐を繰り返している
- けいれんがある
- 麻痺がある(手足が動かない、力が入らない)
- 言葉がうまく話せない、ろれつが回らない
上記のような症状が見られる場合は、迷わず119番に電話し、状況を説明して指示を仰ぎましょう。
判断に迷う場合は、地域の救急相談窓口(#7119)に電話して相談することもできます。 また、かかりつけ医や訪問看護師に連絡を取り、指示を仰ぐのも良いでしょう。
自分で動けない場合・頭を打った場合の注意点
● 自分で動けない場合 ご本人が痛みを訴えたり、意識がもうろうとしているなどで自分で動けない場合は、無理に起こしたり、移動させたりしないでください。 無理な移動は、怪我を悪化させる可能性があります。 その場で楽な姿勢でいてもらい、救急隊員や医療従事者の到着を待ちましょう。
● 頭を打った場合 高齢者の転倒で特に注意が必要なのは、頭部の打撲です。 若い頃と比べて、とっさに手が出にくく、顔や頭を直接打ち付けてしまうことがあります。 頭をぶつけた場合、たとえその場で症状が見られなくても、念のため医療機関を受診し、詳しく検査してもらうことが重要です。
頭部打撲後、数日経ってから硬膜下血腫といった、徐々に脳を圧迫する状態になることもあります。 受診後も、頭痛、吐き気、めまい、話し方の変化(ろれつが回らないなど)、歩き方の変化 など、普段と違う様子がないか数日間は注意深く観察しましょう。
安全な立ち上がり介助(容体が安定している場合)
痛みがなく、救急車を呼ぶ必要がないと判断した場合、ご本人の状態に合わせて安全に立ち上がりを介助します。 無理に一人で介助しようとすると、介護者自身の腰を痛めてしまう可能性もありますので、注意が必要です。
介助の基本:ご本人と介助者の重心を近づける 介助する際は、ご本人になるべく近づき、重心を近づける ことを意識しましょう。 腰を大きく曲げた姿勢での持ち上げは、腰に大きな負担がかかります。
立ち上がり介助の方法
ご本人の身体能力や状況に合わせて、以下の方法を検討します。
1. 椅子を使う方法 この方法は、比較的安全性が高く、介護者の負担も軽減できます。
- まず、安定した椅子を近くに用意します。
- ご本人に四つん這いになるよう促し、難しい場合は介助します。
- 椅子に片手ずつ手をかけ、重心を前に移動させます。
- 片足ずつ、ゆっくりと立ち上がらせます。
- 最初に足を立てた側と反対側に介助者が立つと、支えやすくなります。
- 立ち上がったら、ゆっくりと向きを変え、椅子に座らせます。
2. 前方・後方からの介助 近くに椅子などの支えがない場合や、ご本人がある程度協力できる場合に適しています。
- ご本人の前方または後方に立ち、脇の下や体幹を支え、立ち上がりを補助します。
- ご本人の足がしっかりと床についていることを確認しながら、ゆっくりと引き上げるように介助します。
3. 2人介助 ご本人の体重が重い場合や、全介助が必要な場合は、無理せず2人以上で介助を行いましょう。 一人で無理に持ち上げようとすると、介護者もご本人も怪我をするリスクが高まります。
立ち上がった後も、改めて痛みがないか、体調に変化がないか を確認しましょう。
転倒予防と対策:安心して過ごせる環境づくり
一度転倒が起こると、再び転倒するリスクが高まります。 転倒を予防し、万が一転倒してしまっても大きな怪我につながらないような対策を講じることが重要です。
● 住環境の整備
- 手すりの設置: 廊下、階段、トイレ、浴室など、立ち上がりや移動をサポートする場所に手すりを設置しましょう。
- 滑り止め対策: 床に滑り止めマットを敷いたり、滑りにくい素材の床材を選んだりしましょう。
- 段差の解消: 絨毯の端のめくれや、わずかな段差もつまずきの原因になります。できる限り解消しましょう。
- 十分な照明: 夜間は足元を照らすフットライトなどを設置し、明るさを確保しましょう。
- コード類の整理: 電気コードなどが床に這っていると、引っかかる危険があります。
● 福祉用具の活用
- 大腿骨保護パッド付きズボンや頭部保護帽子: 転倒時の衝撃を和らげる効果が期待できます。
- 衝撃吸収性のある床材: 最近では、転倒時の衝撃を吸収する床材も開発されています。
- 杖や歩行器: バランスが不安定な場合は、適切な福祉用具の使用を検討しましょう。専門家(理学療法士や作業療法士など)に相談することをおすすめします。
● 日常生活での注意
- 急な動作を避ける: ゆっくりとした動作を心がけましょう。
- 体調管理: めまいやふらつきがある時は、無理に動かないようにしましょう。
- 足に合った靴を履く: スリッパや底の滑りやすい靴は避けましょう。
● 連絡手段の確保
- 一人暮らしの場合は、すぐに連絡できる手段を確保しておくことが重要です。
- 電話の子機を手の届く範囲に複数置いておく、緊急連絡サービスの利用などを検討しましょう。
- 離れて暮らしている家族がいる場合は、緊急時の連絡方法や入室方法などを事前に話し合っておきましょう。
● 転倒しても大きな怪我をしないための工夫
- 理学療法士などの専門家による、安全な転び方や起き上がり方の指導を受けるのも有効です。
● 家族の理解と安心できる環境づくり
- ご本人の不安な気持ちに寄り添い、安心して過ごせる環境を整えることが、転倒予防につながります。
おわりに
高齢者の転倒は、誰にでも起こりうる可能性があります。 万が一の事態に備え、この記事で解説した手順を頭に入れておくことで、慌てず冷静に対応し、ご本人の安全を守ることができます。 また、日頃から転倒予防に努め、安心して在宅生活を送れるよう、環境を整えていきましょう。
もし判断に迷うことがあれば、ためらわずに医療機関や専門機関に相談してください。あなたの適切な行動が、大切なご家族の安全と安心につながります。