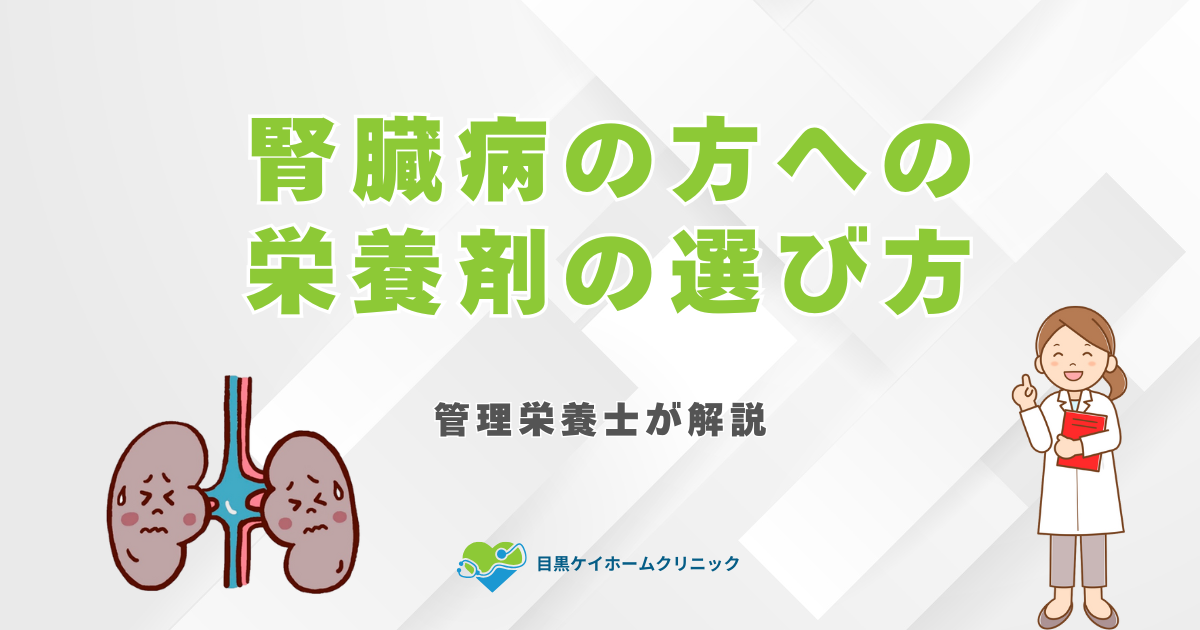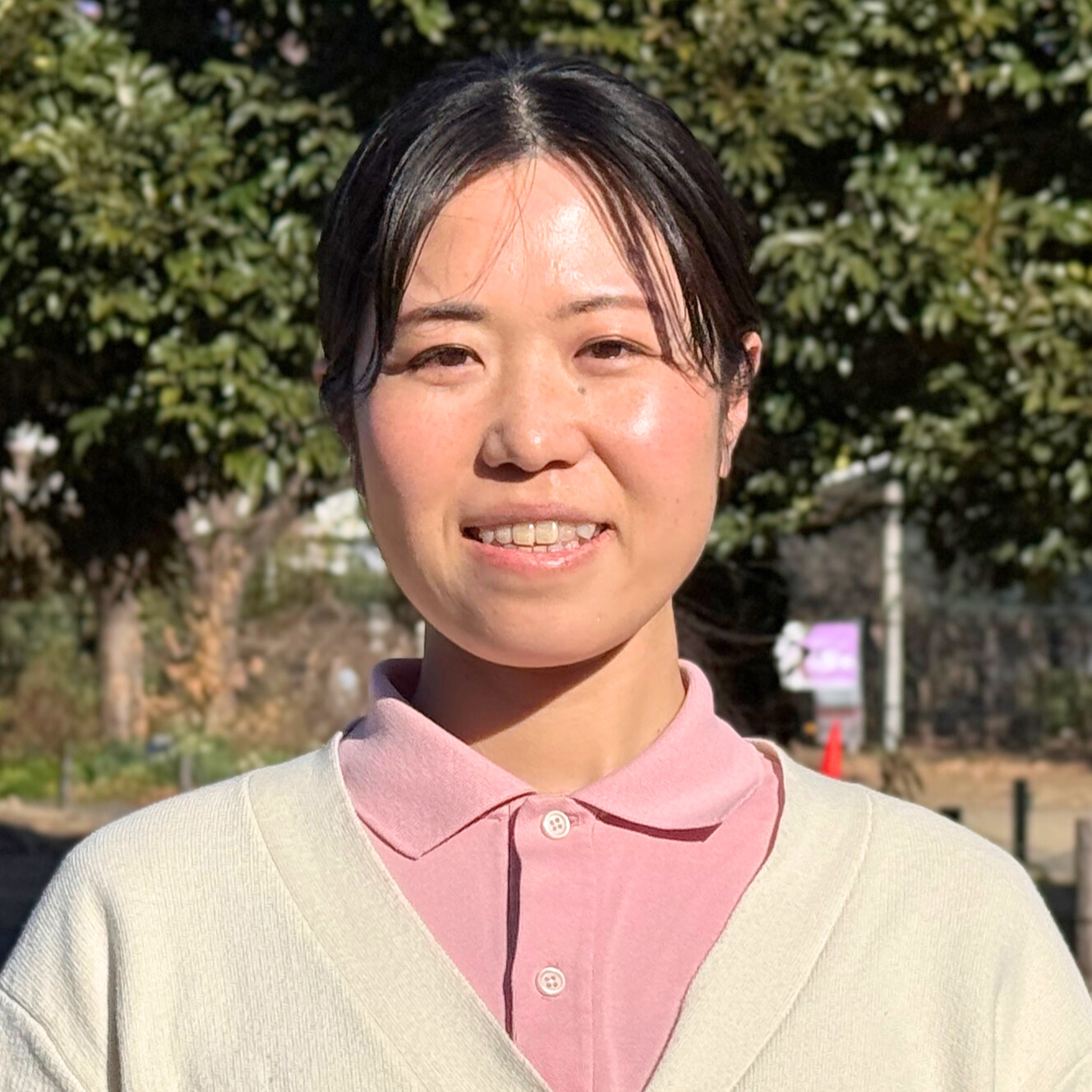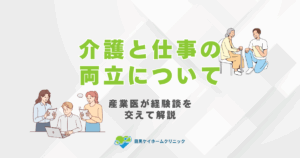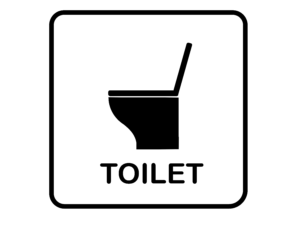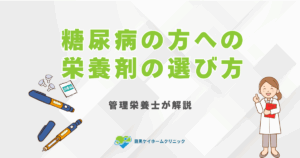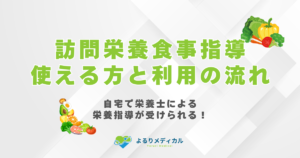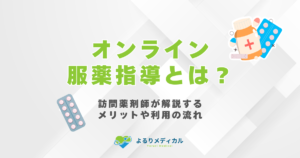腎臓は、体の中の老廃物や余分な水分を排出する大切な臓器。
この腎臓の働きが弱くなる「腎臓病」は、進行すると体にさまざまな影響を与えます。
一般的に、腎臓病の方には「たんぱく質を制限する食事」が必要とされています。
しかし、特に高齢の方では、たんぱく質を減らしすぎると、筋肉が減ってしまったり、貧血になってしまったりすることがあるため、一律にたんぱく質を制限するのはよくないとも言われています。
このため、腎臓病の進行の程度(慢性腎臓病のステージ)や、年齢・栄養状態をよく見きわめたうえで、適切な栄養のとり方や栄養補助食品(栄養剤)を選ぶことが大切です。
今回は、腎臓病の方が適切な栄養剤を選ぶポイントについて解説します。
腎臓病と食事の関係
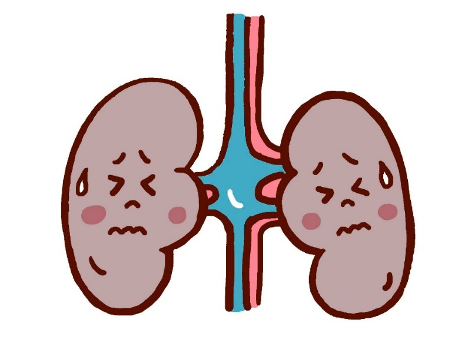
そもそも腎臓は体内でどんな役割があるの?
腎臓はソラマメに似た形をした臓器で腰の辺りに左右1個ずつあります。
腎臓の主な働きは、以下になります。
- 余分な水分や老廃物を排泄する
- ミネラルや酸性度(pH)のバランスを整える
- 血をつくるためのホルモン(造血ホルモン)をつくる
- ビタミンDを活性化して、骨を強くする
- 血圧を調節する
このように、腎臓は体の「ろ過装置」や「ホルモン工場」として、全身の健康を支えています。
腎臓病の食事療法の目的

腎臓の働きが弱くなると、老廃物や水分をうまく排出できなくなり、体にさまざまな影響が出てきます。
そこで大切になるのが、「食事療法」です。食べるものを少し工夫することで、腎臓への負担を軽くし、症状の進行をゆるやかにすることができます。
腎臓病の食事療法のポイントは、主に次の4つです

- たんぱく質をとりすぎないようにする
- しっかりエネルギー(カロリー)をとる
- カリウム・リンをとりすぎないようにする
- 塩分を控える
なぜ「たんぱく質の制限」が必要なの?
腎臓の働きが弱くなってくると、本来なら尿として出されるはずの「老廃物(いらなくなったもの)」が、体の中にたまりやすくなります。
たんぱく質をとると、体の中で使われたあとに「尿素」や「窒素」といった老廃物ができます。腎臓の力が弱っている状態でたんぱく質を多くとりすぎると、これらの老廃物が体内にたまってしまい、腎臓や体に負担をかけてしまうのです。
そのため、老廃物のたまりすぎを防ぎ、腎臓の働きがこれ以上悪くならないようにするために、たんぱく質を“とりすぎないようにする”=たんぱく質の制限が大切になります。
高齢の方は注意が必要です
ただし、たんぱく質を減らしすぎると、体をつくる材料が足りなくなってしまいます。
特に高齢の方は、筋肉が減って体力が落ちたり、低栄養や貧血を起こす原因になることもあります。
そのため、高齢で慢性腎臓病(CKD)のステージ3~5の方では、たんぱく質制限を「ゆるやかにする」「個別に調整する」こともあります。
なぜ「エネルギー(カロリー)」をしっかり摂る必要があるの?
人間の体は、食べ物からエネルギーを得て動いています。
でも、もしエネルギーが不足すると、体は自分の筋肉などを分解して、エネルギーを作ろうとします。
このときに出てくる老廃物は、腎臓で処理されます。
しかし、腎臓の働きが弱っていると、こうした老廃物をうまく外に出せず、体にたまってしまい、腎臓にさらに負担をかけてしまうのです。
だからこそ、腎臓病の方は「たんぱく質を制限する代わりに、しっかりエネルギー(カロリー)をとることが大切」なのです。
ごはん・油・砂糖など、たんぱく質を含まないエネルギー源も上手に使いましょう。
なぜ「カリウム」や「リン」を控える必要があるの?
腎臓の機能が落ちてくると、体にとって不要になったミネラル類(カリウムやリンなど)も、うまく排泄できなくなります。
カリウムが体にたまりすぎると、手足がしびれたり、心臓のリズム(不整脈)が乱れることがあります。
リンがたまりすぎると、血液中のリンの濃度が高くなり、骨からカルシウムが溶け出して、骨がもろくなる(骨粗しょう症)原因になります。
そのため、腎臓病の方は「野菜や乳製品、加工食品などに多く含まれるカリウム・リンを控える工夫」が必要です。
なぜ「塩分」を控える必要があるの?

腎臓は、体の中の塩分と水分のバランスを整えることで、血圧を安定させています。
ところが腎機能が落ちると、塩分を外に出す力が弱くなり、体に塩分と水分がたまりやすくなってしまいます。
すると、
- 血圧が上がる
- むくみが出る
- 心臓や腎臓にさらに負担がかかる
という悪循環につながってしまうのです。
そのため、食塩の量を控える(減塩)ことは、腎臓を守るうえでとても大切なポイントです。
1日の栄養素の目安を考えてみましょう(例)
CKD(慢性腎臓病)の「ステージ」は、腎臓の働き(=GFR:糸球体ろ過量)に応じて5段階に分けられています。これは、腎臓がどれくらい血液をきれいにする力があるかを示す指標です。
| ステージ | 腎機能の値(GFR) | 状態の目安 |
|---|---|---|
| G1 | ≧90 | 正常または高値(しかし腎障害の所見がある) |
| G2 | 60~89 | 軽度の低下 |
| G3a | 45~59 | 軽度~中等度の低下 |
| G3b | 30~44 | 中等度~高度の低下 |
| G4 | 15~29 | 高度の低下(透析療法が必要なレベル) |
| G5 | <15 | 腎不全(透析や腎移植が検討されるレベル) |
腎臓病(CKD)のステージに応じて、下の図の通り、食事療法の目安が変わってきます。
ここでは、CKDステージ4の方(60歳・身長160cm・標準体重56kg)を例に、1日の栄養の目安を見てみましょう。
たんぱく質の目安
56kg × 0.8g = 約45g/日
(※体重1kgあたり0.8gが目安)
エネルギーの目安
56kg × 30kcal = 約1680kcal/日
(※体重1kgあたり30kcalが目安)
カリウム
1500mg以上が推奨されています。
リン
たんぱく質1gあたり約15mgのリンが含まれるため、たんぱく質量を守っていればリンの過剰摂取になることは少ないと考えられます。
| ステージ(GFR) | エネルギー (kcal/kgBW/日) | たんぱく質 (g/kgBW/日) | 食塩 (g/日) | K (mg/日) |
|---|---|---|---|---|
| ステージ1 (GFR ≧90) | 25〜35 | 過剰な摂取をしない | <6.0 | 制限なし |
| ステージ2 (GFR 60〜89) | 過剰な摂取をしない | 制限なし | ||
| ステージ3a (GFR 45〜59) | 0.8〜1.0 | 制限なし | ||
| ステージ3b (GFR 30〜44) | 0.6〜0.8 | ≦2,000 | ||
| ステージ4 (GFR 15〜29) | 0.6〜0.8 | ≦1,500 | ||
| ステージ5 (GFR <15) | 0.6〜0.8 | ≦1,500 |
※1)エネルギーや栄養素量は、適正量を設定するだけでなく、合併する疾患(糖尿病、肥満など)のガイドラインなどを参照して個別に応じて調整する。性別、年齢、身体活動度などにより異なる。
※2)体重は基本的に標準体重(BMI=22)を用いる。
腎臓病の方に適した栄養補助食品(栄養剤)
腎臓病が進んでくると、食事だけでは必要な栄養をとるのが難しくなることがあります。
そんなときに役立つのが「栄養補助食品(栄養剤)」です。
以下のような製品があります。
市販の栄養補助食品(例)


| 商品名 | カロリー | たんぱく質 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| リナレンAA | 200kcal | 0.75g | しっかりエネルギー、低たんぱく |
| リナレンS | 200kcal | 3.0g | たんぱく質を意識したいときに |
いずれも、エネルギーはしっかり補いながら、たんぱく質の摂取量をコントロールできる製品です。
高齢の方など、過度なたんぱく質制限が不要な方にも取り入れやすい設計です。
腎臓病の方向けの経腸栄養剤 (医療用・保険適用外)

| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| リーナレンLP | 400kcal | 4.0g | 低たんぱく・低リン・低カリウム・低ナトリウム、エネルギー補給、腎臓に優しい栄養食品。 |
このような栄養剤は、咀嚼(かむ)や嚥下(のみこみ)が困難な方にも適しており、血糖管理にも配慮された組成になっています。
保険がきかないため、退院後は自己負担になります。入院中は病院の判断で提供される場合があります。
まとめ
腎臓病の方向けの栄養補助食品や栄養剤は、たんぱく質・カリウム・リンを控えることが重視されますが、それだけでは低栄養になるリスクもあります。
だからこそ大切なのは、
- 腎臓の状態(CKDのステージ)
- 年齢や全身の栄養状態
などを考慮して、その方に合った栄養剤を選ぶことです。
自己判断せず、医師や管理栄養士と相談しながら、
栄養と腎臓をバランスよく守っていきましょう。