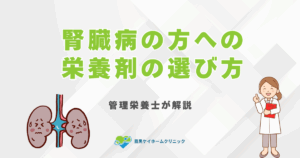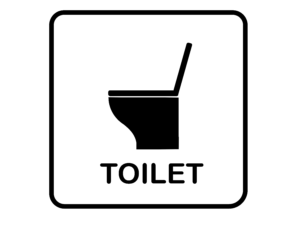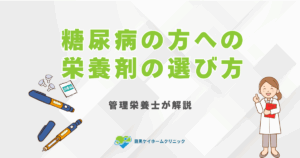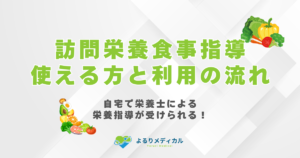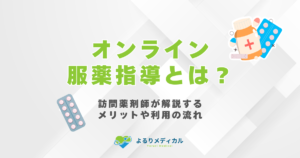日本社会の高齢化が進む中、介護を必要とする家族を支えながら働く労働者が増加しています。仕事と介護の両立は、個人の生活だけでなく、企業や社会全体にとっても重要な課題です。
しかし実際のところ、 “両立支援”がなかなか行き届かず、両立について悩まれている従業員も少なくありません。企業の“両立支援”の現状や課題について本コラムでは考えていきます。
介護と仕事の両立の現状

総務省の調査では、家族等を介護しながら働く人は約365万人、この5年間で20万人近く増加しています。また、年間約10万人が介護を理由に離職しています。
特に40代から50代にかけて離職者が増加し、介護離職が世帯の経済状況に大きな影響を与えることがわかっています。
また、介護が始まる時期と仕事のキャリアの重要な時期が重なることが多く、キャリア形成の障害にもなっています。
介護と仕事の両立における課題
○制度の認知不足: 介護休業制度や介護休暇制度が整備されているものの、労働者への認知が十分でない。
○職場の理解不足: 職場での理解や支援体制が不十分なため、介護に関する相談がしにくい。
○精神的・肉体的負担: 介護と仕事を両立する中で、時間的・精神的な負担が増大し、健康状態が悪化する。
両立支援のための解決策

○制度の活用促進: 介護休業や介護休暇制度の利用を促進するため、社内セミナーや研修を実施する。
○柔軟な働き方の推進: テレワークやフレックスタイム制度を導入し、介護時間の確保を支援する。
○職場での意識改革: 介護に関する理解を深めるために、労働者、管理職向けの研修や相談窓口の設置を行う。
企業の役割と社会のサポート
企業にとって、介護と仕事の両立支援は従業員の定着率向上や人材確保につながります。
政府や自治体による支援制度を積極的に活用し、労働者が安心して介護と仕事を両立できる環境を整備することが求められています。
育児・介護休業法等の改正案が可決・成立
2024年5月24日に育児・介護休業法等の改正案が国会で可決・成立しました。2025年4月1日と2025年10月1日から施行が予定されています。この改正法による変更点の一つに、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等があります。具体的には以下のものになります。
- 両立支援制度|個別周知・意向確認・情報提供・研修等の義務化
- 介護休暇の対象範囲拡大
- 家族を介護する労働者については、努力義務の対象にテレワークを追加
事業者においては、特に改正法によって義務化される内容を正しく理解し、自社における制度や社内規程などを更新することが求められます。
法改正を気に介護と仕事の両立支援制度が整備されるきざし
法改正対策を機に新たな制度やルールについて労働者に周知することや、介護を行う労働者に対して適切に配慮できるように、社内研修などを通じて啓発を行う相談窓口や担当者の設置、周囲のサポート体制、制度を活用しやすい環境つくりも整備できると良いでしょう。
また、介護休業からの職場復帰後においても、介護休暇、所定労働時間短縮、所定外労働の制限等を活用することで、負担を軽減することも大切でしょう。
産業医での経験―介護と仕事を両立するために
介護と仕事の両立は、もはや個人の課題ではなく、会社全体、社会全体で取り組むべき重要なテーマになっています。
私が訪問していた企業で、業務の繁忙に加えて認知症の母親の介護の負担が重なり、メンタル不調で休業された方がいました。
介護体制をつくることの重要性
休職して自分の体調は改善したが、休職中ということで母親の介護を一手に引き受ける形となってしまい、「自分の代わりになる人がいない」「復帰後の介護をどうしたらいいのかわからない」などの理由で復帰の見通しが立たず、長期休職の状態になっていました。
介護保険の認定はうけているものの、サービスは未利用の状態でしたので、産業医面談の際に、
- 介護保険のサービスの利用についてケアマネージャーと相談すること
- 職場の上司にも家庭状況の理解を得ること
を提案しました。休職中に介護体制の構築と復帰後の働き方の調整をすすめることで、本人も復帰の意思が固まり、復帰後も安心して勤務できることになりました。
介護する(ケアラー)側の健康と時間を大切にし、悩みは一人で抱えない
2020年の厚生労働省のアンケート調査では、介護を理由に仕事を辞めた後の自身の変化では、「負担が増した」と回答した割合は、精神面肉体面では50%超、経済面では70%近くに登りました。いずれも負担が減るのではなく、むしろ増したとの回答の割合が高くなっています。
このケースでは両立の負担から休職、そして復職につながりましたが、仕事と介護の両立に関するポイントとしては、
- 「介護する側の健康と時間も大切にする」
- 「一人でかかえこまない」
ということが大切です。
一人でかかえこまないことについては、家族で相談する、かかりつけ医、地域包括支援センターなどの相談先を持っておくことが重要です。社内では、上司や制度に詳しい人事部や総務部、相談窓口への相談することをおすすめします。
会社の外部の窓口としては、以下のサイトでも相談窓口や制度についての情報が提供されています。
介護に関する公的・社内制度を確認し適切に活用する
仕事と介護を両立するためには介護者が、心身ともに健康であることが必須です。
介護では長期的に想定外のことやコントロールできないことが起こり、肉体的な負担や不安や落ち込みなど精神的負担だけでなく、経済的な負担、家庭内や社会生活における役割の変化による負担などにも悩まされます。
その中で、自分の時間の確保をこころがけるだけでなく、あらかじめの準備をすることで想定外のことに対応できる力、早期対応できる力を身につけておくことで、負担の軽減、介護者の不調の予防にもつながります。
制度を理解し、適切に使うためにも、介護保険制度や勤務先の制度を確認しておくのがよいでしょう。そして制度を活用する際にはどの制度をどのように活用するかはケアマネージャーなどの専門家にも相談してみましょう。
出典
総務省 2022年就業構造基本調査
厚生労働省 2019年仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業
厚生労働省リーフレット 育児・介護休業法改正のポイント